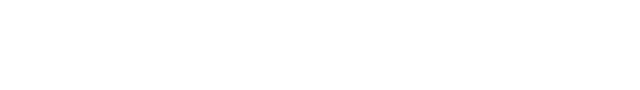便秘症
どんな病気?
- 「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」が便秘症です。具体的にどういうことでしょうか?
- (下剤を使わずに)排便回数が週3回未満。
- 排便時に強くいきむ必要がある。
- 便がウサギのウンチのようにポロポロと小さかったり、硬い。
- 残便感がある。
- 手でなんかしらの介助(指で摘便したり肛門の周囲を圧迫したり)が必要。
- 肛門の閉そく感や排便困難感がある。
- 以上6項目のうち2つ以上当てはまる場合は便秘症です。
- 要するに排便が3日に1回程度であったり排便時になんかしらの困難を感じているようなら「便秘症」とします。
原因は?
- 一番危険な原因は大腸がん。
- 一般的な便秘の原因
✓ 食事量や食物繊維成分が少なく便の量が減ること
✓ お薬の副作用(薬剤性)
✓ 過敏性腸症候群
✓ 骨盤内の筋力低下(腹圧をかけられないなど)
✓ 他の病気(脳梗塞、パーキンソン病、人工透析患者さんなど)に伴うもの 等 - 朝食を摂らない方、女性は便秘になりやすいと報告されています。
女性の便秘症は男性の3.5倍みられ、ダイエット経験のある女性や昼食の量が少ない方も便秘になりやすいようです。
症状は?
- 腹痛、腹部膨満感、排便困難感、残便感など。
- それらによる「日常生活の質の低下」が一番困るところです。
- 便秘症の方は大腸がんになり易いと言われていますが、実は明確な証拠はありません。
- 便秘症の方は、便秘のない方と比べて寿命が短く、心臓や血管の病気、腎臓病などにかかり易いことが明らかになってきました。
どんな検査があるの?
- まずは大腸がんが隠れていないか調べることが重要です。これには大腸カメラが必要になります。
- 検便(便潜血検査)では一部のがんしか陽性になりません。(矛盾するようですが、大腸がん検診としては非常に優れた検査です。)
- 一般的なCT検査でも、がんが大きくなければ写ってきません。
- 他に原因がないか調べるために血液検査、尿検査などが必要な場合もあります。
治療は?
生活習慣面
- 適切な食事(適度な食物繊維の摂取)
- 適度な運動
- 1日15分・週5回のお腹マッサージも有効とされています
- 乳酸菌、ビフィズス菌などの摂取
内服薬について
- 「センノシド」「プルゼニド」と言ったような下剤がよく使用されてきた歴史がありますが、実は依存性があり長く使い続けると徐々に自力での排便が困難になる心配が出てきます。
- これは「刺激性下剤」と呼ばれます。刺激性下剤は頓服、または短期間での使用に留めた方が良いでしょう。
*どうしても刺激性下剤が必要な方は一定数いらっしゃいます。 - 「刺激性下剤」に加えて「膨張性下剤」「浸透圧性下剤」「上皮機能変容薬」「胆汁酸トランスポーター阻害剤」「漢方薬」など多数のタイプがあります。
- あるタイプの下剤効果が今一つでも他のタイプも試す、他も加えるなどして便秘解消を目指すことが可能です。諦めず、快適な日常生活を目指して治療を受けてみてはどうでしょうか。
参考
慢性便秘症診療ガイドライン2017
この記事を執筆した人
金沢憲由
日本消化器病学会 消化器病専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医
日本肝臓学会 肝臓専門医
日本内科学会 総合内科専門医
日本消化管学会 胃腸科専門医
難病指定医
秋田大学出身
月間400件以上の内視鏡検査を行なう。
丁寧でわかりやすい医療の提供を志す。
人間ドックによる予防医療にも注力している。